皆さん、こんにちは!
本日は「やすとものいたって真剣です」(朝日放送テレビ)で紹介されたお店を取り上げます。
2025年9月25日放送回に登場の「笹屋伊織」です。
ここは1716年(享保元年)創業、300年以上の歴史を持つ京菓子の老舗です。当主は「有職菓子司」として、京都御所・神社仏閣、茶道家元などにも御菓子を納める伝統を継いできました。
そんな格式ある店でありながら、「どら焼」という比較的庶民的なお菓子を、しかし極めて凝った形で世に出したのがこの代表銘菓です。
このどら焼、店のサイトでも「えっ!これがどら焼ですか?」という表現がある通り、一見して印象に残る斬新さを秘めています。
では、この「6つの不思議」とも言われる特徴を順に見ていきましょう。
笹屋伊織「どら焼」の6つの不思議

えっ、これがどら焼?(公式サイトより)
1.名前の不思議
江戸時代末期、五代目当主・笹屋伊兵衛が、京都・東寺のお坊さんから「副食となる菓子を作ってほしい」との依頼を受けました。
お寺で使う「鉄板」は容易でないため、代替としてお寺にあった「銅鑼(どら)」を焼き台に用い、生地を焼いたことから、「どら焼」と名付けられたと伝えられます。
この名づけの由来が、一般的などら焼の語源説(鉄板説、銅鑼説など)と重なる点も興味深いものです。
2.カタチの不思議
一般的などら焼は、丸い皮と皮の間に餡を挟む形ですが、笹屋伊織のものは少し異なります。まず、生地を鉄板上に流し、それに「棒状にしたこし餡」を転がすようにして包む方式を採ります。
その結果、もっちりとした薄皮が年輪のように巻かれ、円柱型(長細い棒状)となるのが特徴です。
この形式は、和菓子でいう“棹菓子(さおがし)”の形式にも近く、羊羹に次いで古い棹菓子に類するという評価もあります。
3.卵が入っていない不思議

お坊さんの副食用として設計されたという背景から、生地には卵を一切使っていません。仏教の教えで「殺生」を禁じられていたため、動物性の材料(卵など)を用いないようにしたという配慮です。
このため、甘味・食感を出すには別の工夫(粉の配合や蒸し具合、焼き技術)を要することになります。
4.毎月3日間だけの不思議
このどら焼は、普段は店頭に並ぶものではありません。発祥時は、東寺にだけ納めるお菓子として限定されていました。
その後、町中へ広まり要望が出るようになるも、大量生産が難しいため、弘法大師の月命日「弘法さん(21日)」に合わせて販売する方式が採られました。
1975年からはこの範囲を拡げ、毎月「20・21・22日」の3日間のみ販売というルールになりました。
そのため、実質「幻のどら焼」「月に3日しか出会えないお菓子」として語られるようになっています。
ちなみにオンラインショップでの予約・発送もこの販売期間に合わせており、通常は毎月19~21日に発送されるよう設定されています。
|
|
5.竹の皮の不思議
このどら焼は、竹の皮に包まれて提供されます。竹の皮は伝統的に抗菌性を持つ素材として、食材の保存や衛生に用いられてきました。
また、竹皮ごと切ることで、手を汚さずに皮をむきながら食べられるように設計されています。
ただし、竹皮自体は食べるものではなく、あくまで包装素材です。
6.召し上がり方の不思議
このどら焼は、常温でそのまま味わっても十分楽しめる設計ですが、さらに以下のようなアレンジも推奨されています。
1. 温める(電子レンジ、蒸し器など)
2. 焼く(オーブントースターやフライパンで)※竹皮を外し、幅2 cm程度に切ってから
3. 揚げる(天ぷら風に)※竹皮を外して輪切りにして調理
4. 冷やす(冷やして、ワインやウイスキーと合わせる楽しみ方も提案されています)
これらのバリエーションで、もちもちとした皮の食感や上質なこし餡の風味をさまざまな表情で味わうことができます。
実際の味わい・評価・留意点
実際に食べたレビューでは、「もちもちした食感」「甘さ控えめで上品」「素材感を感じられる余裕ある甘味」という感想が散見されますね。
通常のどら焼とは異なる“ロール状”“棹菓子風”という形態から、見た目でも驚かれることが多く、「これがどら焼?」といったリアクションを引き起こす点が特色です。
販売期間が限定されているため、買い逃すと入手が難しいという点が、希少性を高めています。
商品としては、1棹単品(1,944円程度)や詰め合わせ、2棹・3棹入り、行器入り仕様などが提供されています。
賞味期限は製造後7日程度と、日持ちはそこまで長くはありません。
なぜテレビで紹介されるのか —— 注目される理由
1. 希少性・限定性
毎月3日間のみの販売という希少性は、話題性として十分です。消費者が「出会えたらラッキー」と感じる演出があります。
2. これがどら焼?という驚き
見た目・形・食感が従来のどら焼とは大きく異なるため、視覚的インパクトがあります。
3. 歴史性とストーリー性
お寺に納めたこと、銅鑼焼発祥説、仏教に関する戒律に配慮した設計など、背景に物語性があります。
4. 味と技術の融合
卵不使用・薄皮ロール包みの製法など、高い技術と素材の選択が感じられる点が、和菓子ファン・グルメ層を惹きつけます。
5. 贈答・話題性ギフトとしての価値
限定性と話のタネになるという点で、手土産やギフト向けの商品価値が高まります。
お店は何店舗か、ありますね。もちろんどら焼以外の商品もいろいろそろっています。

本店・イオリカフェ
住所:京都市下京区七条通大宮西入花畑町86
電話番号:075-371-3333
営業時間:9:00~17:00 ※カフェ:ラストオーダー16:30
定休日:火曜日
※どら焼の販売日(毎月20日・21日・22日)が火曜日にあたる場合は営業しております。
代わりに他の平日が振替休日になります。
アクセス:JR「京都」駅中央改札口から徒歩20分
京都市バス「七条大宮・京都市水族館前」停留所から徒歩1分
まとめ
本日は「やすとものいたって真剣です」で紹介された京都の老舗和菓子店「笹屋伊織」のどら焼を取り上げました。番組を見て、まさに「えっ、これがどら焼き?」と思ったのです。通販で取り寄せて食べてみたいものですね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cc1ee11.c08f35e8.4cc1ee12.1a63895b/?me_id=1385906&item_id=10006163&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff261009-kyoto%2Fcabinet%2Fiori%2Fb-be15_thm.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

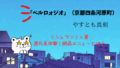
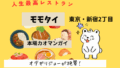
コメント